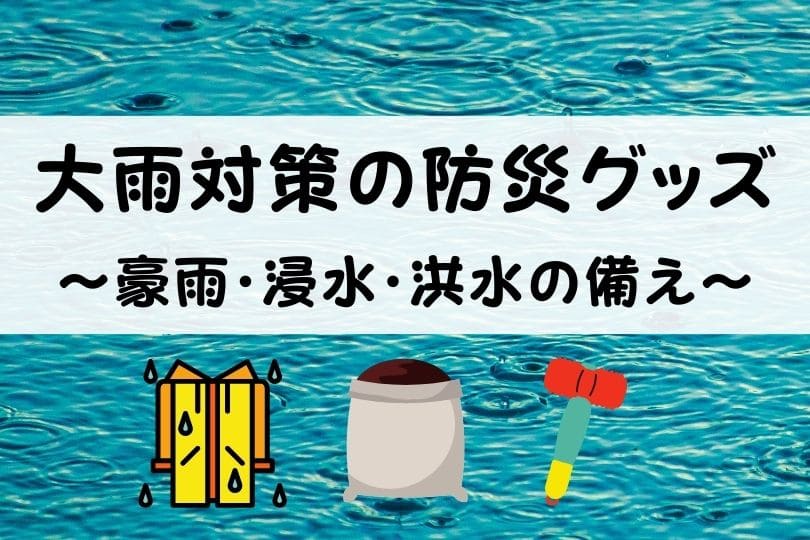- 大雨・豪雨・水害の対策グッズのおすすめリスト
- 誰でも今すぐ実践できる大雨・豪雨・水害対策
近年では大雨・豪雨など水害 (浸水・洪水) による被害が増えています。
名前のついた大雨災害でいえば『令和2年7月豪雨』と称される熊本県を中心とした九州地方の集中豪雨により、多くの住宅が水害に遭いました。



日本各地において、数年のあいだで毎年のように大雨による災害が発生しています。
この記事では、大雨・豪雨・水害の対策グッズのおすすめリストと、誰でも今すぐ実践できる大雨対策を解説します。
大雨対策グッズのおすすめリスト
大雨対策グッズのおすすめリストは、以下の通りです。
【避難対策】
| レインコート | 雨の中を非難するため |
|---|---|
| 脱出ハンマー | 車のドアが開かない時に脱出するため |
【浸水対策】
| 土嚢(どのう) | 床上浸水を防ぐため |
|---|---|
| 止水版(しすいばん) | |
| 段ボール・ゴミ袋 | 水嚢(すいのう)を作るため |
レインコート
レインコートは雨の中を移動するために必須グッズです。
おすすめは、上下セパレートタイプのレインコート。
- フィット感があり動きやすい
- 身体がしっかりと覆われるため濡れにくい
一方、コンビニやスーパーではワンピースタイプのレインコートも売っていますが、防災という観点では有効性は低いです。
- 身体にフィットしないため動きづらい
- ワンピースの下からはみ出た足が濡れる
動きづらいと避難に遅れてしまったり、雨に濡れて身体が冷えると体力を奪われてしまうため、上下セパレートタイプのレインコートを選んでおきましょう。
持ち出し用防災グッズですでにレインコートを備えている場合は、あらためて購入する必要はありません。
小さい子供がいる家庭ではベビー・キッズ用のレインコートも用意しておきましょう。



子供用は、かんたんに着させられて雨を防げるロンパースタイプがおすすめです。
100均でもレインコートが売っている場合がありますが、素材が薄いため破れやすく、濡れると張りつき動きづらいです。しっかりとした素材のものを備えるようにしましょう。
脱出ハンマー
脱出ハンマーは、車のドアが開かなくなったときに窓を割って脱出するための防災グッズ。
大雨で冠水した道路に侵入して車が動かなくなり、水圧でドアが開かなくなるということもあります。



過去の大雨災害で車ごと流されてしまうという例もあります。
突然の大雨による水害に備えて、社内に1つ脱出ハンマーを用意しておきましょう。
ただ、脱出ハンマーは他の防災グッズのように事前に試すことができないためJIS規格(日本産業規格:日本の国家規格)を選ぶと安心です。
土嚢(どのう)
住宅の床上浸水対策として土嚢(どのう)を使用します。
土嚢というと『土』をイメージしやすいですが、平時に土をあらかじめ入れて備えておくことは現実的ではありません。土は重くて運ぶのも大変ですしね。
一般家庭でのおすすめは吸水ポリマー性(水を吸って膨らむ)の土嚢です。
【吸水ポリマー性の性質】
| 状態 | 厚さ | 重さ |
|---|---|---|
| 通常時 | 3~5mm | 100~200g |
| 吸水時 | 10cm前後 | 10~15kg |
通常時は非常にコンパクトなため省スペースで保管しておける上、使用後に乾燥すると再び薄くなるので処分もかんたんです。



土嚢は、緊急時の水害に備えて吸水速度の速いものがおすすめ。
膨張するまで通常3~5分かかりますが、こちらの土嚢は1分で済むので緊急性の高い水害でも安心して使用することができます。
大雨・豪雨時には下水が逆流して、トイレや排水溝から浸水する場合があります。
玄関やドアの外側対策だけでなく、便器の中や排水溝の上など内側対策も忘れずに行いましょう。
止水板(しすいばん)
止水版(しすいばん)は、名前の通り水を止めるための防災グッズで、住宅や地下へ雨水が流れ込むのを防ぎます。
基本的には法人向けの商品が多いため問い合わせが必要ですが、一般家庭にも止水版が販売されています。
段ボール・ゴミ袋
段ボールとゴミ袋は、備えていた土嚢や止水板で浸水を防ぎきれない場合の水嚢(すいのう)として使用します。



水嚢の作り方は簡単ですよ。
水嚢の作り方
- ゴミ袋を二重にして水を入れる
- 空気を抜いて口をしばる
- 段ボールの中に水嚢を詰める
あまり水を入れすぎると重たくなり、持ち運びが大変です。
体力に自信のない方は、小さい袋で水嚢をたくさん作る方が負担を減らすことができます。
基本的に浸水対策は土嚢や止水板が有効ですが、トイレや排水溝など住宅内部の逆流防止には水嚢でも充分対応できますよ。
誰でも今すぐできる大雨・豪雨・水害対策
大雨・豪雨による水害(浸水・洪水)対策として防災グッズを揃える以外に、今すぐできる対策を紹介します。
3〜7日分の備蓄をする
大雨・豪雨により停電や断水の可能性があります。
そのような場合に、3日分(大規模災害では7日分)の食料・飲料・生活必需品の備蓄をするよう農林水産省では推奨しています。
- 飲料水(1人1日3L)
- 非常食(ご飯、バスケット、乾パンなど)
- 生活必需品(トイレットペーパー、カセットコンロなど)



水は飲料だけでなく生活用水も必要なため、忘れずに備えておきましょう。
※非常食については、以下のサイトを参考にしてください。
関連リンク(外部サイト)
>>【非常食】お菓子のおすすめ9選!実食口コミレビュー【2020年版】
ハザードマップを確認する
ハザードマップは、自然災害による被災が想定される区域や避難場所、避難経路を表示した図のことです。
国土交通省が運営するハザードマップポータルサイトで、事前に自宅や通勤・通学地周辺の災害リスクを確認しておきましょう。
ハザードマップの見方は、内閣府の避難行動フローで解説しているので、合わせて確認するとわかりやすいです。
防災アプリをダウンロードする
防災アプリは、最新の災害情報を知れるだけでなく、避難場所の登録や家族の安全を確認するものもあります。
防災アプリは基本無料で使えますが、事前に地点登録が必要なものもあるため早めにダウンロードしておきましょう。
▶ 【2021年最新】 おすすめの防災アプリはこちら
過去の大雨災害は7〜10月に多い



2021年8月まで、過去10年で発生した大雨災害をまとめました。
| 大雨・豪雨 | 被害状況 |
|---|---|
| 平成23年7月新潟・福島豪雨 (2011年7月27日~30日) | 4日間で7月の月間降水量平年値の2倍以上の大雨が降った。 死者・行方不明者6人、床上・床下浸水約9000棟 |
| 台風12号による豪雨 (2011年8月30日~9月5日) | 長時間にわたって広範囲で大雨が降って、和歌山県、奈良県、三重県で土砂災害や河川氾濫が発生した。 死者・行方不明者98人 |
| 平成24年7月九州北部豪雨 (2012年7月11日~14日) | 熊本県の熊本地方・阿蘇地方、大分県西部で局地的な大雨が長時間降り続いた。 死者・行方不明者33人、床下浸水8409棟など |
| 平成26年8月豪雨 (2014年7月30日~8月20日) | 2つの台風と停滞前線により広範囲に大雨が降った。広島市では土石流やがけ崩れが多発。 (災害関連死含む)死者77人、家屋の全半壊396棟など |
| 平成27年関東・東北豪雨 (2015年9月7日) | 西日本から北日本にかけての広範囲で大雨が降った。鬼怒川の堤防が決壊。 死者14人、家屋の全半壊7000棟、床上・床下浸水1万5000棟以上など |
| 平成29年7月九州北部豪雨 (2017年6月30日~7月1日) | 西日本から東日本を中心として局地的に大雨が降った。福岡県、大分県を中心に大規模な土砂災害が発生。 死者・行方不明者42人、家屋の全半壊・床上浸水1600棟超 |
| 平成30年7月豪雨 (2018年6月28日~7月8日) | 梅雨前線と台風7号の影響で、西日本を中心に長時間の広い範囲における大雨が降った。西日本各地で河川氾濫、浸水、土砂災害等が発生。 死者・行方不明者232人、家屋全壊6758棟・半壊1万878棟・一部破損3917棟、床上浸水8567棟、床下浸水21913棟など |
| 台風19号による大雨・暴風 (令和元年10月10日~10月13日) | 関東甲信・東北地方で記録的な大雨。災害救助法適用自治体が390市区町村と、東日本大震災を超える適用。 死者・行方不明者89人、家屋の全壊3273棟、半壊28306棟、一部破損35437棟、床上浸水7666棟、床下浸水21890棟など |
| 令和2年7月豪雨 (2020年7月3日~7月31日) | 熊本県を中心に九州や中部地方などで発生した集中豪雨。 死者78人、行方不明者4人、家屋全壊270棟・半壊575棟・一部破損778棟、床上浸水7474棟、床下浸水7526棟など |
| 台風第10号による暴風、大雨等 (2020年9月4日~9月7日) | 南西諸島や九州を中心に暴風、大雨、高波、高潮を発生させた大型台風。 死者3人、行方不明3人、重傷者20人、軽傷者90人、家屋全壊7棟、半壊40棟、一部破損1637棟、床上浸水31棟、床下浸水236棟など |
| 7月1日から3日の東海地方・関東地方南部を中心とした大雨 (2021年7月1日~7月3日) | 東海地方・関東地方南部を中心に大雨。 死者22人、行方不明者6人、重傷者1人、軽傷者9人、家屋全壊7棟、半壊54棟、一部破損202棟、床上浸水388棟、床下浸水1914棟など |
| 前線による大雨 (2021年8月11日~8月19日) | 西日本から東日本の広範囲に及ぼした大雨。 死者13人、重傷者2人、軽傷者14人、家屋全壊27棟、半壊80棟、一部破損205棟、床上浸水2421棟、床下浸水5666棟など |
上記の表を見てわかるように、大雨・豪雨は7月にもっとも多く発生しています。
次いで8月~10月に台風も発生しやすく、大雨・豪雨による災害リスクが高まります。
まとめ:大雨対策は平時の備えが大切
大雨災害は毎年のように発生しています。それも毎年規模が大きくなっていますよね。
大雨は例年7〜10月に多く発生していますが、いつどこで発生するかわからず、発生すると被害も甚大なため平時の備えが大切です。
ただ、この記事で紹介したものは、あくまで大雨により発生する水害の対策グッズ。
基本となる防災グッズは先にしっかり備えておきましょう。